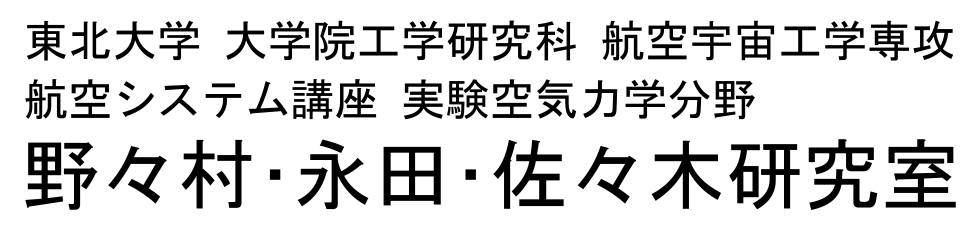(作成:2019/09/23; 最終更新: 2020/05/22)
※永田個人の体験に基づいているので言わずもがな,指導教員や他の研究者,先輩の話もよく聞いてみてください.学位取得に関する項目は指導教員に必ず確認.
この記事を見ているあなたは博士進学を考えているかもしれないし,あるいは今でこそ博士課程への進学を考えていないかもしれないがこのあと急に進学したくなるかもしれない.人生何が起こるかわからない.一度博士過程への進学を考えたが色々考えてやめた人にいたってはなおさらである.兎にも角にもまずは知ること,そして備えることで可能性を広げておくことが重要.国際共同大学院や学際高等研究教育院などに修士から入る場合は,取得単位などに要件があるのでとりあえず申請要件を満たすように単位を取得しておくと万一進学したくなった場合にも対応できる.反対に,もう諦めたからと指定の授業をたった数単位取らなかったことによって,気が変わった際に過去の自分の選択を嘆くこととなる.可能性は常に広げておくべきである(誰かが言ってた).
・博士号の意味(色々な先生がこういう感じのことを言っている気がする)
研究者の運転免許(すごい研究ができることではない)
「解くべき問題を自ら設定し,調べ,考え,解析して結論を導き,一般に発表する」一連の流れを習得すること
ちなみに,卒論は「与えられた問題を与えられた方法で解く」,修論は「与えられた問題を自分で考えて解く」,博論は「自分で考えた問題を自分で考えて解く」ことで完成すると言っている先生もいた.
・お金 (各種奨学金を参照)
何を差し置いてもお金は大事。学内の学位取得プログラムはM2からもらえるものがある.M1の9月あたりからプログラムごとに徐々に締め切りを迎える(国際共同大学院が9月半ば,学際高等研究教育院が3月頭)ので進学を決意したら早めに教員と相談する.もちろん博士になってからも応募できるので焦らず検討する.ただし,指導教員を同じくする複数の大学院生の応募を認めないプログラムもあるので要注意(研究テーマもそうだが先に決意していたほうが基本的には優先される).東北大は学振の書類添削や学内の学位プログラム,大学・研究科・学科の補助制度,企業からの奨学金など支援が非常に充実しているのでとにかく応募できるものにはすべて応募する.そうすればよっぽどのことがない限り何かしら取れている気がする.過去の申請書の一部は共有ドライブの中に入っているので参照するとよい.
・博士号取得要件 (2022/04/04更新)
- 前提:講義の単位を取得すること
- 3 本の査読付きジャーナルを主著者(もしくは応答著者 として掲載させる.(後
輩の修論などで書いても OK, 博論とジャンルが違う内容でも OK
- 東北大学機械系の博士論文は序論,3章分のスタンドアローンな研究内容,
結論で構成される.博士論文のテーマに沿った3 章分の内容があればOK - ジャーナ ルの内容と 3 章の内容が被っていても被っていなくても OK.
相談の上 1 ジャーナルが 2 章分になったり, 2 章分が 1 ジャーナルになっていても OK
授業を受けて単位を取得し英文査読付き(IF付き)ジャーナルを3本以上publishする,またはその見込みが立つと審査を受けられるらしい.12月中に中間審査(実質の本番),1月半ばに最終審査(公聴会)がある。博士論文は英文で作成し発表は日本語でもよい (国際共同大学院の人は海外の大学院の先生を副査に入れるので発表も英語).
・副査の先生について
審査員は教授3名を含む准教授以上4名がミニマム.2019年度の体制では浅井先生が主査で副査に野々村先生,残り教授2名以上を選ぶ.10月頭に希望の先生をリストアップして指導教員に提出.審査の労力が集中しないように調整し最終的には指導教員が副査の先生を選ぶ.
・主な日程(令和元年度)
| 10月頭 | タイトルやら副査の先生の決定 |
| 11月頭 | 予備審査の日程決定 |
| 12月中旬 | 予備審査発表練習 & 副査の先生へ論文お届け |
| 予備審査3日前 | 博論提出 |
| 12/24, 25 | 予備審査 |
| 1/14 | 博論提出締め切り |
| 1/15 | 本審査発表練習 |
| 1/16 | 本審査 |
| 1/22 | 判定会議 |
| 2/10の週(忘れた) | 博論最終締め切り |
・タイムライン(永田の場合)
| 3月 |
気がついたらD2終了目前.年明けからなんだかやる気が出ない (睡眠のリズムがとても悪い). 博論に向けて体力をつけようと決意した.とりあえず週3日・1日4 km走ることにした (3/11). |
| 4月 |
気がついたらD3になっていた。まさかD3になる日が来るとは思わなかった。 |
| 8月 |
野々村先生に呼び出されてCRESTのポスドクの話を再度された (8/6). なんやかんやしているうちに夏になった。9月から博論を書き始めようと決意した。走るのだけはなんやかんや続いているので毎日5 km走ることにした (8/12). |
| 9月 |
なんやかんやしているうちに9月も終盤、ひとまず博論のファイルを作成した(9/23)。 そうこうしているうちに野々村先生に呼び出され仮テーマを決め副査の先生候補も考えた (9/26). 学振PDの1次審査の結果が返ってきた.面接には残った (9/30). |
| 10月 |
ゼミで博論の目次と大まかな内容を発表した.基本的に過去に出した論文の内容を論文ごとに章分けして構成したところResults and Discussionsの章は基本的に3章でなければならないと言われた.論文3本出てるはずだから3章にはなるよね,という意味かと思っていたら3章でなければならないということだったらしい.ちなみに4章立ては検討の余地があるらしいが,それ以上だとひっくり返して通すとか通さないとか何やらものすごい雰囲気で言われたので安易な気持ちで章立てを考えてははいけない.修論とはだいぶ雰囲気が違うことを実感.とにかく言われたことは確実に守らないとえらいことになりそう.副査の先生はいつの間にか先生方の提案が共有サーバーのエクセルにかかれていて特に意見を聞かれることはなかったのであまり悩む必要はなかった,というか先生方の人選をひっくり返すのはそれこそ大変なことである(10/1). なんやかんや4章構成になった.あと副査の先生も1人チェンジした.違うと思ったことは言っておいたほうが良いらしい (10/8). 週一で横田と卓球を始めた.草間先生もたまに来る.やはり運動は良いらしい (10/16). |
| 11月 |
映画を見ていたら11月になってしまった.とりあえず出版済みの論文をコピペした.あと1ヶ月しかないと思うと結構やばい気もする.予備審査の日程はいつの間にか決まった (11/5). とりあえず全項目を一応書いた.図の作り直しなどの脳死作業の量が多い.小さい頃から図の元データと編集可能データとプロットのスクリプトをちゃんと整理しておかないと大変なことになるのでこれから博士に行こうとする人はきっちり整理しておくと過去の自分の偉大さに涙が出そうになると思う (11/29). |
| 12月 |
学振PDの面接を受けた.既に他のところに決まっているので受けなくても良かったが何かあると死ぬのと経験値のためと思って受けた.スライド作成と練習に結構時間を使った.N先生に「え,行かないのに受けるの?」と言われた意味が分かった (12/4).9月末までなんやかんやしていただけだった自分にキレそう. 予備審査のスライド作成を開始.クソ長い (12/8). N先生に博論のイントロの英語が全然だめと言われる事件発生 (12/10). スライドが大体完成.各章のタイトル含め全部で55枚くらいにしないと確実に1時間超える.スライドを作ったことで博論全体で書き方に一貫性がない部分が結構ありそうだということに気がつく(章内では一貫性は取れているがバラバラに書いていたのでこんな事になったと思われる).来週頭に副査の先生にお届けなのに.ついでにN君の修論をベースに書いて投稿していた論文が返ってきたのでrevise開始 (12/11).そこに飛び込んできたPoFの査読依頼,前にResearchGateでコメントを求められた人の論文だったので受けた (12/12). 予備審査の発表練習終了.個人的な練習のときは57分くらいに収まっていたのに+10分かかってしまった(スライドは51枚).というかそもそも1時間喋らなければならないというわけではないらしい.イントロ以外のスライドは問題ない感じだった(英語がおかしいことを除いて),逆に心配になってきた.物理の議論などは本当に重要なことだけで良いらしい(後は質疑でということだと思う).イントロは社会的な問題とのつながりなど学会では話さないような大きな視点のスライド1枚(ここに普段学会での1枚目のスライドも含める?),自分の研究の直接的背景,どこまで分かっていてどこから分かっていないのか・何を明らかにすべきなのか,合計3枚程度で作るっぽい.永田の場合は最終目標からかなり遠いところをやっているので4枚ということになりそう(混相流一般の話,混相流の数値計算の話・混相流モデルの必要性,非圧縮・圧縮性混相流モデルの現状,圧縮性低Reynolds数流れの研究動向).とにかく喉が渇く.伝わっているかな?とか余計なことを考えると説明が長くなってしまうのでしっかり作り込んで練習した上で淡々とこなすように意識したい.伝わらなかった部分は質疑で死ぬほど聞かれるわけだし (12/4). 予備審査が終わった。予定されていた時間は発表1時間、質疑1時間だがおよその目安ということらしく,必ず1時間殴られるというものではないらしい.永田の場合は発表1時間程度で質疑は25分程度だった.Outlookは作って添付しておくだけでいいかと思って練習していなかったが浅井先生が発表しないの的な感じでじっとこちらを見てきたので結局発表した(多分喋りすぎた). 学振PDの2次審査の結果が返ってきた.補欠合格だった (12/26). |
| 1月 |
年が明けた.年末年始は星の写真撮りに行ったり博論と関係ない論文のReviseしたり水平になってひたすらAmazon Primeで映画を観たりと一度博論を完全に忘れて安静にしていた.とりあえず本審査用のスライドを作ってみたが30分だとほとんど喋れないことに気がつく.今の所各章結果のスライドは2枚程度.週明けから本気出す (1/4). 博論の副本提出完了.書式が微妙に違ったりして修正を要求されるので事務への提出は早めに行ったほうが良い (1/14). 本審査の発表練習が終了.土壇場でハイフンの使い方を指摘される.あろうことかタイトルでもハイフンの使い方を間違えていて修正届けを先生に出していただく羽目に(本当に申し訳ありません).そしてすでに提出済みだった副本にボールペンでハイフンを足すというイベントが発生.ついでに略歴の落丁も判明し事務の方にめっちゃ笑われた.色々とよく確認したほうがよい.とにかく早く終わってほしい (1/15). 本審査終了.緊張しすぎて自分が何を喋っているかよく分からなかった.完全に理解していた話も少し前に解決したものだとその瞬間で答えられなかったりして悲しい気持ちになる.予備審査同様中身に関する質問に加えて今後の発展や分野への貢献など広めの質問も来た.ともかく無事に終わったので良かった.みんなで焼き肉を食べた (1/16). 判定会議が終了.本審査が終了した段階で学生ができることはなくなる.博論の付箋でコメントが入った副本が返却されるので修正する.あとは提出物を忘れずに出せば良い (1/22). |
| 3月 |
学振PDの補欠結果が開示された.通った.学振PD一本だけだと完全に手遅れになりかねないのでこれ一本という線は考えられないなと思った (3/2). 博論の製本版を作成していないことに気がつく.製本は生協で申し込める.上製本とレザック製本があり印刷済みの紙を持ち込んで製本のみして貰う場合は上製本が5000円程度,レザック製本が500円程度.印刷も込でやってもらうと一冊1万円を超える(もちろん研究費で出せない,学振も無理)のでamazonなど紙を買って印刷して持っていくのがお財布には優しい.紙は中厚口や厚口のA4上質紙(密度のことだと思うが70 kgとか90 kgとか書いてある).大体5営業日くらいで上がってくる.申込時は表紙と背表紙に記載する文字列も印刷して本文の紙束と一緒に生協に預ける.お金は後払い. 誰に配るか,上製本かレザック製本かは悩みどころだが審査委員会の先生方は上製本をお渡しするのが無難?永田の場合は審査委員の先生+博論に含まれる内容の論文の共著者の先生方に配布した. |
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.