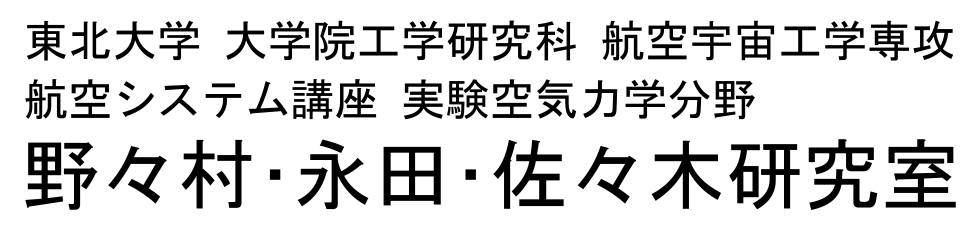(最終更新: 2020/04/02)
研究が捗る気がする基本無料のソフトウェアやサイト.便利ツールあったら教えて下さい.
Overleaf
N先生主導で研究室に導入されつつあるオンラインLaTexエディタ.ほぼ正式採用されていると言っても過言ではない.オンラインでの複数人による共同編集が可能でかなり便利.EmacsやVimのキーバインドもそれなりに対応しておりエディタとしても優秀.ただしブラウザのショートカットキーが重複しているのでChromeとかだとありとあらゆるキーバインドが予約済みで無力,しかもあろうことかChromeのキーバインドはそう簡単に無効化できない,Edgeだとキーバインドは大体使えるがプレビュー機能がすこぶる調子悪い,Waterfoxはkeyconfigというadd-inを入れる(Waterfoxでリンク先一番上のkeyconfig.xpiをクリックするとインストールされる)ことでショートカットキーを自由に制御できる上プレビューも問題ない(by 伊吹)ので幸せになりたければWaterfoxを使うべし.作業中のアカウントのシンボルが画面に表示される仕様なので書いている途中でN先生のアイコンが点灯すると焦る.無料アカウントは共同編集人数と校正機能に制限があるが野々村先生が有料アカウントを持っているので,自分でプロジェクトを立ち上げた後に野々村先生に共有し参加してもらい管理者権限を野々村先生に譲渡するのが手っ取り早い(共有-> 野々村先生のアドレスを入力し実行,野々村先生が参加すると権限を変更できるようになるので編集可能から管理者に変更して実行,譲渡完了).最近は学位論文をOverleafで書く人も割といる.Web版のみでオフラインで作業できないのが多分唯一の難点.LaTexで書くのが面倒な表や複雑な数式などはweb上の作成ツールを使うとよい(ページ下部参照).
Web版のみ.
Grammarly
英文校正ツール.昔N先生がaeroallで流していたが何故かあまり浸透していなかった.最近はユーザーも増えつつある.MS Word,Chromeなどいくつかのソフト上で動作するアドオンを配布している.Grammaryが動いているChromeでgoogle翻訳を開いて英文を書いて日本語で確認するのが最強(by 小澤さん).こいつで拾える程度のミスを連発している文章を展開すると(当たり前だけど)怒られるので注意 (体験談).
DeepL
付畳み込みニューラルネットワークを使った機械翻訳ツール.Googleより自然(2020.03.23現在)な翻訳を可能にしているらしく,その界隈が衝撃を受けていた.Google翻訳もこれを受けて進化するかも・・・?ただ結構意訳されたり文法的に間違っていてもいい感じに翻訳してくれるので自分で書いた英語を日本語訳して文法確認するツールとしては使えない.
Trello
付箋ツール.試した中で一番使いやすかった.何をやらなきゃいけないのか・何をやったのかすぐ忘れてしまい,やったかどうか・忘れていないかを確認することにリソースを割いてしまう人におすすめ.共有機能もあるのでなかなか仕事が進まない人にToDo listを作って送りつけることも可能.
Windows (win8以上),MacOS, iOS, Android, Web.
Mendeley
文献管理ソフト.研究室公式としてはJabrefを運用しているがこちらの方が近代的 (文献の情報などが自動で入る,文献内まで検索できる,など).そして東北大は実は機関アカウントが使える(2019年から?).大学がいつまで契約を続けてくれるかは分からないので正式採用は難しいか.無料アカウントでも容量は少ないが個人レベルでは問題なく使えるのとiOS, AndroidアプリとPCで同期がとれるので外で論文読んだりする時に楽.取り込んでる文献の情報から関連しそうな文献をサジェストしてくれる機能もある(ありがたい).
Windows, MacOS, iOS, Android,web版.
MarginNote
文書閲覧ソフト.論文用というわけではないがアプリ上でハイライトやコメントを入れるとその部分のテキストが抜き出されてメモが作成される.階層を作ってメモを整理したり色々できる.ボヘーっと論文を読んで結局後で読み直すことが多い人や論文を読んでも細かい内容をすぐに忘れてしまう人におすすめ.iCloud経由で同期もできる.
MacOS, iOS.
Inkscape
ドロー系ソフトウェア.一部地域で市民権を得つつあるので正式採用も近い?論文の図を作る時に使っている.例えばGnuplotで吐き出したepsのプロットを複数読んで複合プロットを作ったり矢印や文字を入れたりする時に使っている.あと,複雑な凡例や数式などはおとなしく後入れしたほうが明らかに楽.修正用にsvgで保存しepsやpdfで書き出したものをOverleafに貼っている.学術雑誌は図をベクトル画像で個別に提出するよう要求されるので普段からそれに対応した形で進めておくと後で不毛な作業をせずにすむ.
Windows, MacOS, Linux.
Gsys
グラフから数値データを読み取るソフト.画像上で軸とその範囲を指定してあげてシンボルをマウスでポチポチ選択すると数値データを吐き出してくれる.他のは使ったこと無いけどとりあえずこれで困ったことはない.
Windows, MacOS, Linux.
Gnuplot
グラフ作成ソフト.布教しようとしているが一部のおじさんしか使っていない(Matlabで解析している人が多いので仕方ない).epsで吐き出した時に線や文字の情報が自然(不自然にグルーピングされていたり細切れになっていることが少ない(KaleidaGraphは結構しんどい)ので結構好き.入力データと出力の様式が一目で分かるので人のデータで論文を書く時に楽な気がする.でも普及しない.
Windows, MacOS, Linux.
ResearchGate
研究者向けのSNS.学会論文なども結構上がってて(全文ではない)割と情報が落ちてる.閲覧履歴から関連しそうな文献をサジェストしてくれる(ありがたい).iOS, Android, web版.
MathType
数式入力ツール.MS wordで使える.2017年くらいに消滅してしまったMS 数式エディタの拡張版.ショートカットキーを覚えればマウスでポチポチ数式を入力する不毛な作業から開放される.無料版で十分だと思っていたが有料版だとLaTexのコードを吐ける.Windows, MacOS.
Google Scholar
Googleが提供する学術論文検索のためのWebサービス.論文の検索で御用達と思うが,キーワードを設定しておけばそれに関連する論文が新しく出た時にメールを飛ばしてくれる(ありがたい)ので設定すべし.
web版のみ.
Microsoft Academic
Microsoft Researchが提供する学術論文検索のためのWebサービス.Google Scholarがキーワード検索で動作するのに対してMicrosoft Academicはセマンティクス検索ができるらしい(なんかすごそう).とりあえずMicrosoftで走っていた自然言語処理のプロジェクトの成果物を使ったサービスらしく,検索者の入力の意味を汲み取って文献の内容に基づいた検索結果を提示してくる.文献のサジェストも何やら工夫がされているらしい.これから使ってみたい.
web版のみ.
Academic Accelerator
まだあまり良くわかっていないがとりあえず論文誌のIFとか雑誌名の略称(ISO4でどう略すべきか規則が決められている)を調べたりするときに使っている.
Connected Papers
論文同士のつながりを可視化するサービス.関連研究を見つけるときに便利.
Google Books Ngram Viewer
英単語の使用頻度を比較できるサービス.異分野の学会発表や論文出版をする際に便利.2つ以上の単語でどちらを使おうか迷ったときは基本的に使用頻度の高いものを利用すべき.Web版のみ.(by岩崎)
ブラウザ上で動作するLaTex向けサービス
LaTex Tables Generator
表を作れる.罫線とかが微妙に使いづらい.
Mathpix Snipping Tool
数式の画像からLatex数式のソースを吐き出してくれる.
Texcount web service
.texファイルを投げるとコンパイル後の文字数を出してくれる.
amsmathパッケージ参考サイト
数式を打つ時にお世話になるamsmathパッケージ.色々コマンドがあるけれど忘れがち.そんなときのための参考サイト.
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.